「療育って本当に必要なの?」そんな疑問を持つ保護者の方は少なくありません。特に、グレーゾーンと呼ばれる子どもたちは、明確な診断がなくても「ちょっと気になる」部分があり、支援を受けるべきか迷うことも多いです。この記事では、療育の目的や意味、そして家庭でできるサポート方法について、専門家であり母親でもある私の視点からお伝えします。
療育ってそもそも何?
「療育」と聞くと、特別な訓練や治療をイメージされる方が多いかもしれません。
でも、本来の療育とは「その子がその子らしく育つための関わり方」のことです。
遊びや日常生活の中で、「できた!」を増やしていくサポートです。
たとえば、片付けが苦手な子には「まず1個だけ片づけよう」と声をかけることで、自信をつけていきます。療育は“がんばらせる”のではなく、“できる環境を整える”ことなのです。
グレーゾーンの子どもが抱える小さな困りごと
私が関わってきたある男の子は、学校ではよく注意されるけれど、家では穏やかに過ごせるタイプでした。
先生からは「集中力がない」と言われていましたが、よく観察すると、椅子の高さや机の位置が合っていなかったのです。
グレーゾーンの子どもたちは、発達の特性が少し見られるものの、生活に大きな支障がないことも多いです。
しかし、ちょっとした環境のズレが「落ち着かない」「やる気が出ない」につながることがあります。
「まだ大丈夫」と思っていた時期にこそ必要な支援
多くの保護者は「様子を見よう」と考えがちです。
でも、困りごとが小さいうちにサポートすることが、後の大きな困難を防ぐことにつながります。
療育は、診断がある子だけのものではありません。
たとえば、苦手な動作を練習したり、気持ちを表現する練習をしたりすることで、学校生活がぐっと楽になります。
「ちょっと気になるけど病気ではない」という段階こそ、環境や関わり方を見直すチャンスです。
療育でできることとは?
療育の現場では、子どもが「楽しい」と感じられる活動を通して成長をサポートします。
たとえば、バランス遊びで体の使い方を学んだり、グループ活動で順番を待つ練習をしたりします。
この積み重ねが、学校生活や社会性の土台になります。
また、療育の中では「保護者のサポート」も大切にしています。
家庭での接し方や声かけを一緒に考えることで、子どもにとって安心できる環境が広がっていきます。
家庭でできるサポートと環境づくり
家庭でも、無理なくできる工夫があります。
たとえば、「できたことを見つけてほめる」「やるべきことを見える形にする」などです。
カレンダーやイラストで予定を伝えると、安心して行動できます。
また、生活のリズムを整えることも大切です。
寝る時間や食事のタイミングを一定にすると、気持ちが安定しやすくなります。
小さな積み重ねが、子どもの「自分でできた」という達成感を育てます。
私が開発に関わった「イーチェスク」と座りやすさの工夫
私が開発に関わった「イーチェスク」は、発達特性のある子どもたちの“座りにくさ”に着目した学習机です。
座面や机の高さを調整しなくても、自然に正しい姿勢をとりやすい形にしています。
療育では、「姿勢が安定する」ことが集中力につながります。
椅子や机が合わないだけで、子どもは疲れやすくなり、落ち着かないこともあります。
イーチェスクのように、子どもの体に合った家具は、支援の第一歩といえるでしょう。
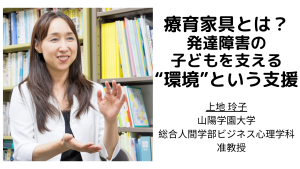
まとめ
療育は、特別なことではなく、子ども一人ひとりに合った関わりを考えることです。
グレーゾーンの子どもたちは、「困りごとを見えにくく抱えている」ことが多いですが、
その小さなサインに気づいてあげることが何よりの支援です。
「うちの子も、もしかして…?」と思ったときが、サポートを始めるタイミングです。
家庭でできる工夫や環境づくりから、一歩を踏み出してみませんか。
コメント欄で、皆さんの体験や工夫もぜひ教えてください。
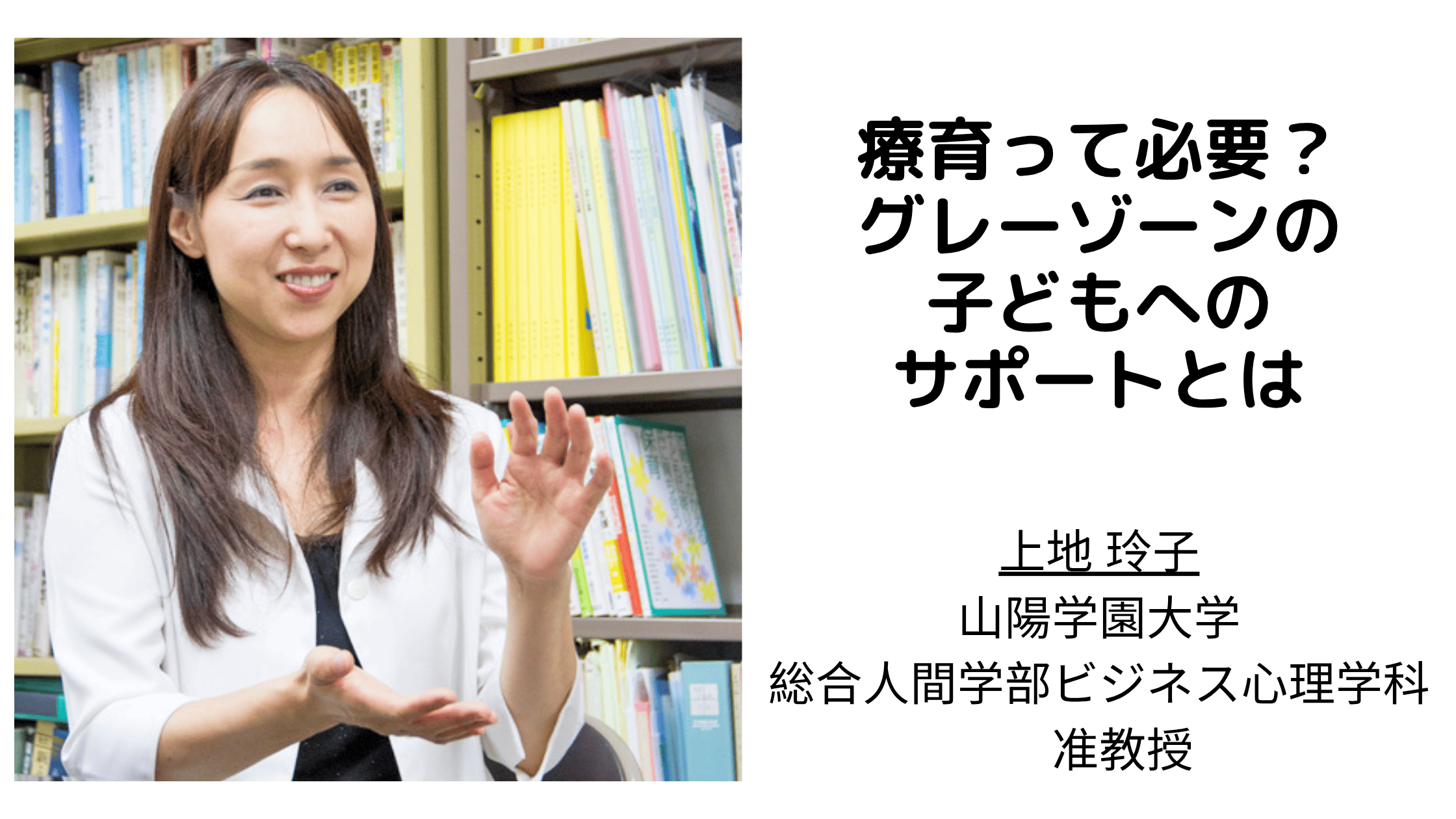
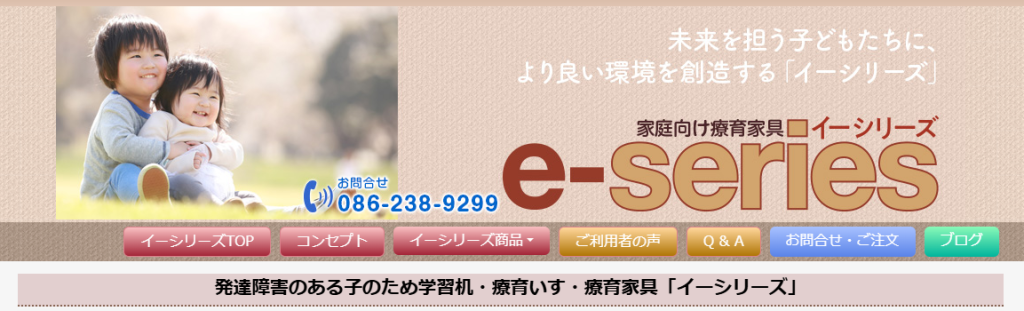
コメント