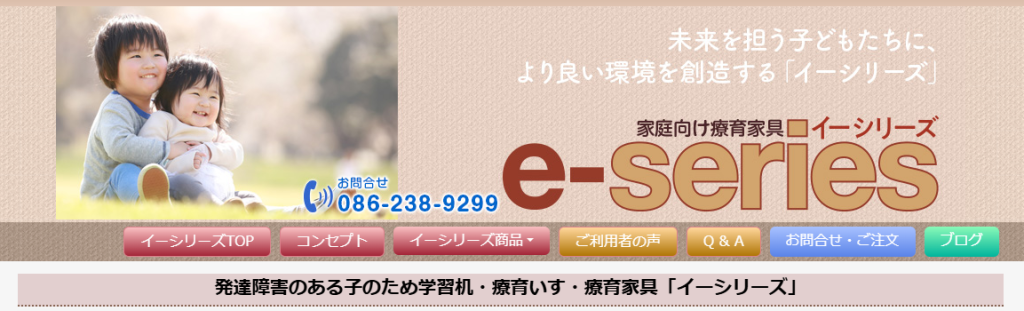「うちの子、どうして座っていられないの?」そんな悩みを抱えるママは少なくありません。特にグレーゾーンや発達特性のある子どもにとって、じっと座ることはとても難しい課題のひとつです。けれど、それは子どもの努力不足ではなく、環境のせいかもしれません。本記事では、家庭でできる工夫や、子どもの発達をやさしく支える「療育家具」という選択肢について、専門家であり母でもある私がわかりやすくお話しします。
「落ち着いて座れない」わが子に悩むママへ ― 家庭でできる発達支援とは?
「宿題を始めてもすぐに立ち歩いてしまう」「ごはんの時間に落ち着いて座れない」。そんな子どもの姿を見て、困っているママは少なくありません。私が関わってきた家庭でも、同じような相談をよく受けます。これは子どもが「やる気がないから」ではなく、体や感覚の特性が関係していることが多いのです。
なぜ「座れない」のか?グレーゾーンの子どもが抱える背景
座れない理由にはいくつかあります。たとえば、ADHDの特性で体を動かさずにいることが苦手な場合や、椅子や机が合わずに不安定で落ち着かない場合です。ある子は「足が床につかないと落ち着かない」と言っていました。つまり「座れない」のは、子ども自身の努力不足ではなく、環境の影響が大きいのです。
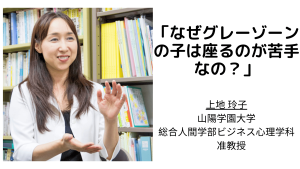
家庭でできる支援の第一歩 ― 環境を整えることがカギ
家庭でできる支援の基本は「安心できる環境をつくること」です。テレビの音を消して静かにしたり、照明を落として集中しやすい雰囲気にしたりすることが効果的です。また、子どもが安心できる「自分の場所」をつくるだけで変化が見られることもあります。私が関わったある家庭では、小さな机を用意しただけで子どもが自然と座りやすくなり、勉強への集中が長く続いたのです。
療育家具という選択肢 ― 普通の家具と何が違うの?
ここで注目してほしいのが「療育家具」です。療育家具とは、発達に特性のある子どもが安心して使えるように工夫された家具のことです。
たとえば、
- 足がしっかり床につく椅子
- 背中やお尻をやさしく支えて体を安定させる椅子
- 子どもの成長に合わせて高さや角度を変えられる机
普通の家具は大人基準で作られていることが多く、子どもに合わないことがあります。ですが療育家具は「座りやすい」「疲れにくい」「安全」を大切に作られているのが特徴です。
そして何より大切なのは、家庭に療育家具があれば「座る」練習を自然にできるということです。施設や教室に通わなくても、家の中で日常的に椅子に座るトレーニングができます。毎日の食事や宿題の時間が、無理なく「座る」練習の場になるのです。
実際に、足置きや手すりがついた椅子に変えただけで「前より落ち着いて座れるようになった」という子もいました。家庭での小さな積み重ねが、子どもの「座る力」を伸ばし、自己肯定感を育てるきっかけになるのです。
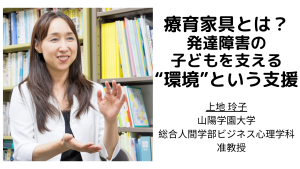
「座れる」環境が未来を変える ― ママができる一歩から始めよう
療育家具は、子どもの「落ち着いて過ごす力」を支える道具であり、ママの気持ちを軽くしてくれる存在でもあります。「姿勢を直しなさい」と繰り返さなくてもよくなり、子どもとの時間がもっと楽しくなるのです。大切なのは、「環境を整えること」から始めてみること。家庭での小さな工夫や家具の工夫が、子どもの未来を変える一歩につながります。
まとめ
「座れない」ことに悩むとき、つい子どもを責めてしまいそうになります。けれど、その背景には必ず理由があり、環境を整えることで子どもは大きく変わることがあります。療育家具は、子どもの体を支え、集中しやすくするだけでなく、ママの心の負担も軽くしてくれる“やさしい支援”です。あなたのお子さんに合った工夫は何でしょうか?ぜひコメントで教えてくださいね。