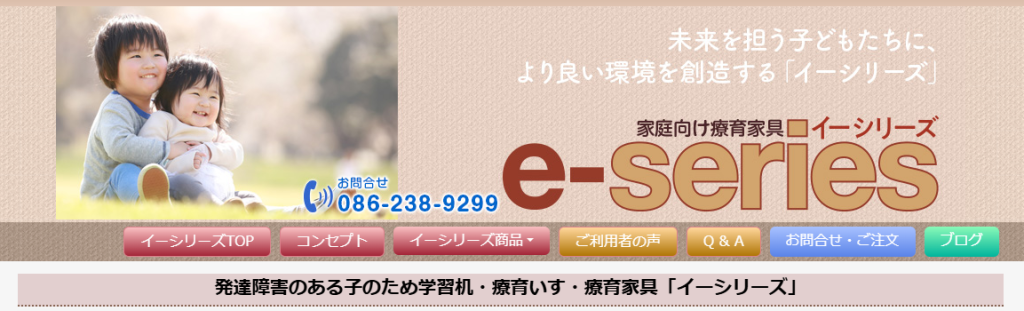「うちの子、ちょっと気になるけど、病気ではないって言われた…」そんなふうに感じたことはありませんか?グレーゾーンの子どもたちは、発達に特性があるけれど診断がつかない場合も多く、学校や家庭で“見えにくい困りごと”を抱えています。このブログでは、そんな子どもたちにどう寄り添えばいいかを、支援に関わる専門家としての経験をもとに、わかりやすくお話しします。子どもの「生きづらさ」に気づき、日常の中でできる支え方を一緒に考えてみませんか?
「ちょっと気になる子」に見えて、本当は困っている
ある小学校で、「○○ちゃんはマイペースで、ちょっと変わってるね」と言われていた子がいました。先生も友だちも悪気はありませんが、実はその子は集団の中でとてもがんばっていて、でも周りにはその“がんばり”が見えていませんでした。
「グレーゾーン」とは、発達障がいとまでは診断されないけれど、社会や学校生活で困りごとを抱えている状態のこと。子ども本人も、自分がなぜうまくいかないのかわからず、つらさを感じている場合があります。
気づかれにくい“見えない困りごと”とは?
ある放課後等デイサービスで、元気そうに見える男の子が、帰りの時間になると「もうダメ!」と突然泣き出しました。先生たちはびっくり。でもそれは、がんばりすぎて疲れが限界だったからでした。
また、別の子は、毎日のように宿題を忘れてきました。でも、それは「やらなかった」わけではなく、ランドセルに入れたつもりが入っていなかったり、時間の感覚がつかみにくかったりすることが原因でした。
このように、ADHDや自閉スペクトラムに近い特性を持つ子は、「わざとやらない」のではなく、「できない理由」が見えにくいのです。
母として悩んだ日々──“わが子を理解する”ことから始まった支援
私が関わったあるお母さんは、「先生から“甘やかしすぎ”って言われました」と涙ぐんでいました。でもその子は、教室の中で音やにおいにとても敏感で、毎日緊張していたのです。
大人が「困った子」と思ってしまう行動も、実は「困っている子」からのサインかもしれません。
子どもの行動を見て、「なぜこうなるの?」と感じたときは、まず子どもの気持ちに目を向けてみましょう。そして、その子の「得意なこと」「苦手なこと」を一緒に見つけていくことが、支援のはじまりになります。
家庭でできる!“ちょっとした配慮”が子どもの世界を変える
私が携わった支援先の家庭では、子どもが学習に集中できず、毎日の宿題が親子バトルの原因になっていました。そこで、子どもの目線に合わせた机とイスを用意し、机の上に「やることリスト」を貼ってみたところ、「一人でやれる!」と自信が出てきたのです。
環境を少し工夫するだけで、子どもの集中力や安心感は大きく変わります。怒るより、「できるしくみ」をつくってあげる。たとえば、タイマーで時間を見えるようにしたり、やる順番を絵カードで示したりする方法も効果的です。
“グレーゾーン”という名前に縛られずに
「うちの子、なんでこんなことができないの?」と悩む日もあるかもしれません。でも、できないことの裏には、その子の特性があります。そして、それに気づいて寄り添うだけで、子どもはぐんと安心し、自分の力を発揮できるようになります。
大事なのは、「診断の有無」よりも、「その子らしさ」に気づくこと。グレーゾーンという言葉にとらわれすぎず、子どもと一緒に少しずつ歩んでいきましょう。ひとりで抱え込まず、支援の手を借りることも、親として大切な選択です。
まとめ
子どもが何に困っているのか、どうすれば楽になるのか、一緒に考えていくことで、親子の関係もやわらかくなります。「うちの子もそうかもしれない」「似たようなことで悩んでいます」など、あなたの感じたことをぜひコメントで教えてください。この記事が、少しでも子育てのヒントになれば嬉しいです。あなたの声が、同じ悩みをもつ誰かの勇気にもなります。