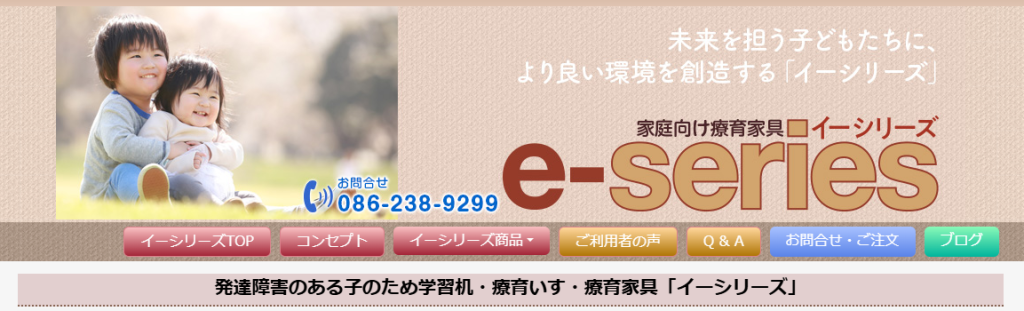「うちの子、どうして椅子に座っていられないんだろう?」そんな悩みを持つお母さんへ。ADHDや発達障がいのある子どもたちは、じっと座ることが苦手な場合があります。でも、それにはちゃんと理由があるのです。この記事では、障がい児教育の専門家であり母親でもある私が、自宅でも実践できる「座れるようになる3つのポイント」を、わかりやすくお伝えします。
はじめに:「うちの子、どうして座っていられないの?」
「5分も椅子にいられない」「すぐ立ち歩いてしまう」――そんな悩みを抱えるお母さんは少なくありません。
私も同じ経験をしました。私は大学で障害児教育を研究しつつ、発達障がいのある子どもを育てる母でもあります。専門知識があっても、わが子が椅子からすぐ離れてしまう場面では戸惑いました。
この記事では、発達障がい(とくにADHD)の子が“座っていられる”ようになるために大切な3つのポイントを、できるだけわかりやすい言葉でお伝えします。読み終えるころには、今日から試せるヒントが見つかるはずです。
ポイント①「身体の感覚」を理解する:じっとしていられないのには理由がある
発達障がいの子の多くは、身体の感覚が普通とは少しちがいます。
感覚が敏感な子は、イスの硬さや服のタグがチクチクするだけで落ち着きません。
逆に鈍感な子は、からだを強く動かさないと“座っている”感覚がつかめず、ゆらゆら揺れたり立ち上がったりします。
家でできる感覚調整のヒント
1. 足を安定させる
足がブラブラすると落ち着きません。足台や低い箱を置き、しっかり床につくようにしましょう。
2. クッションやざらざらシート
座面に薄いクッションや滑り止めシートを敷くと、椅子の感触がやわらぎ安心します。
3. 短い時間から始める
まずは1~2分だけ「静かに座る」経験を作り、少しずつ時間を延ばします。
ポイント②「環境を整える」:座れる場所は“育てる”もの
子どもが集中して座れるかどうかは、家具や周りの環境にも大きく左右されます。
椅子・机のサイズを見直す
イスはひざが直角になる高さが目安。高すぎても低すぎても姿勢が崩れ、すぐ動きたくなります。
机の高さは、ひじを曲げて軽く机に乗るくらいがベスト。
療育家具の活用
私は仲間と一緒に、学習机「イーチェスク」を開発しました。角度調整こそできませんが、高さを細かく変えられ、足台もセットできます。市販品でも、似たポイントを満たすものを選べば十分です。
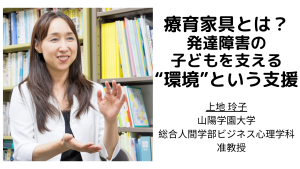
空間づくりのコツ
1. 音:テレビやスマホの通知音を切り、静かなBGMか無音に。
2. 光:まぶしすぎる照明は避け、やわらかい間接光を。
3. モノの配置:机の上は最小限。視界におもちゃが入ると気が散りやすくなります。
ポイント③「関わり方を工夫する」:座れた!を育てるコミュニケーション
どんなに環境を整えても、声かけや見守り方が合わないと子どもは安心して座れません。
前向きな言い換え
×「ちゃんと座りなさい!」
〇「あと30秒だけ、一緒に静かにしてみようね」
「まだ難しいだけ」「練習中」という視点で声をかけると、子どもは責められていると感じにくくなります。
成功体験を積み重ねる
タイマー作戦:キッチンタイマーや砂時計で「あと○分」を見える化。できたら大げさにほめる。
小さなごほうび:短く座れたらシール1枚、5枚たまったら好きな遊びを5分――と少しずつ達成感を味わわせます。
家庭と療育の連携
保育園や療育センターの先生に「家ではこうしています」と共有し、同じ方法を採用してもらうと子どもは混乱しません。逆に施設でうまくいった方法を家庭に取り入れるのも効果的です。
まとめ
発達障がいのある子どもが「座れる」ようになるには、無理やり叱って座らせるのではなく、感覚や環境、関わり方を工夫することが大切です。一歩ずつできたことを積み重ねることで、子どもは「座れる自分」に自信を持てるようになります。家庭でも取り組める工夫から始めて、子どもと一緒に成長していきましょう。
おわりに:座れるようになることはゴールじゃない
「座れるようになった!」――これは大きな一歩ですが、子どもの成長はここで終わりではありません。私たち親子も、うまく座れた日もあれば、できない日もありました。
大切なのは、子どもが安心して過ごせる環境と、チャレンジを支える大人のまなざしです。お母さん自身が疲れたときは、周囲の支援を遠慮なく頼ってください。
一人で抱え込まず、子どもと一緒に少しずつ“できた!”を積み重ねていきましょう。今日の記事が、その第一歩になれば幸いです。