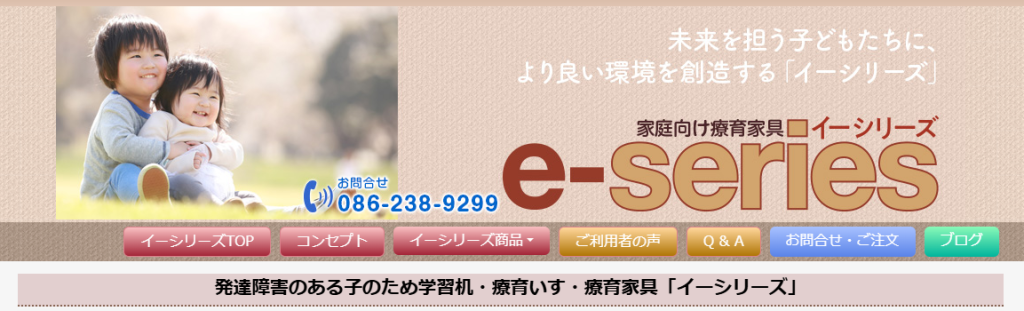「じっと座っていられない」「すぐに立ち歩く」「集中が続かない」──そんなお子さんの姿に悩んだことはありませんか?それは、子ども自身の努力不足ではなく、“環境”のせいかもしれません。この記事では、発達障害やADHDの子どもたちの「落ち着いて過ごす力」を支える『療育家具』について、専門家であり母親でもある著者が、やさしく解説します。家庭でできる支援の第一歩として、ぜひご覧ください。
「うちの子、どうして落ち着かないの?」そんな悩みから始まった“療育家具”という選択
「うちの子、どうしてじっと座っていられないの?」「いつも机に向かってもすぐに立ち歩いてしまう…」
そんな悩みを抱えているお母さんは、きっと少なくありません。
私もそのひとりでした。子どもが集中できないのは、本人のやる気がないからではありません。実は、体をうまく支えられなかったり感覚が敏感だったりといった特性が原因になっていることもあるのです。
そんな中で出会ったのが、「療育家具(りょういくかぐ)」という考え方でした。家具=モノだと思っていた私ですが、使う子どもに合わせて工夫された家具には、子どもの発達をやさしく支える力があると気づいたのです。
療育家具とは?普通の家具と何が違うの?
「療育家具」とは、発達に課題のある子どもたちが安心して使えるように作られた家具のことです。主に机やイスなど、毎日の生活や学びに使うものが中心です。
たとえば、
- 足がしっかり床につくイス
- 体が安定するように背中やお尻を支えてくれるイス
- 子どもの成長に合わせて高さや角度を変えられる机
などが挙げられます。
普通の家具は、大人が基準で作られていたり、子ども向けでもサイズが合わないことがあります。ですが療育家具は、 「座りやすい」「疲れにくい」「安全」 を大切にして作られているのが特徴です。
たとえば、「イーチェア」や「イーチェスク」は、子どもの身体に合わせて調整できるだけでなく、手すりや足置きもついているので、体をしっかり支えることができます。
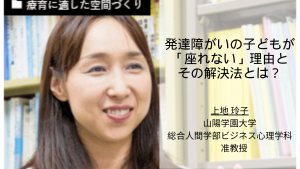
なぜ今、家庭に「療育家具」が必要なのか?
療育家具は、施設や学校だけでなく、家庭でも大きな力を発揮します。
発達障害やADHDの子どもは、姿勢を保つのが苦手なことがあります。姿勢が崩れると、集中しにくくなったり、イライラしやすくなったりします。
でも、イスがしっかり体を支えてくれていたら、体に力を入れすぎなくてもすむので、気持ちも落ち着きやすくなるのです。
家庭に療育家具があると、
- 宿題の時間がスムーズになる
- ごはんのときにじっと座っていられる
- お母さんの声かけが少なくてすむ
といった変化が生まれることがあります。
毎日使う家具だからこそ、家の中での小さな困りごとを減らす支援になってくれるのです。
療育家具が生まれた背景──母としての実体験から開発へ
私は専門家として、発達障害のある子どもたちと関わる仕事をしています。でも、それ以上に、ひとりの母親として、子育ての大変さを知っています。
わが子のために「もっと楽に座れるイスがほしい」「落ち着いて宿題に向かえる机がほしい」と感じたことが、療育家具づくりの始まりでした。
家具職人さんとの出会いをきっかけに、試作品を作り、何度も改良を重ねました。その過程で、「うちの子にも使わせたい」という他のお母さんたちの声をたくさんいただきました。
専門知識と実体験の両方を活かして、「子どもの安心と成長を応援する家具」を形にしたのが、「イーチェスク」「イーチェア」などの療育家具シリーズです。
療育家具が支えるのは、子どもだけじゃない。ママの心にも、安心を。
療育家具は、子どものためのものですが、実はお母さんたちの心にも寄り添う道具です。
「姿勢を直しなさい」と何度も言わなくてもよくなったり、「ちゃんと座ってくれるかな」と心配せずにすんだり。
子どもが変わると、家庭の空気も変わります。
「特別な支援」は大げさに聞こえるかもしれません。でも、家具を変えるだけで、 日常の中でできる“やさしい療育” があるのです。
お子さんの困りごとに悩んでいるお母さん。まずは「環境を整えること」から始めてみませんか? それは、子どもとあなた自身を、少しラクにしてくれる一歩になるかもしれません。
記事のまとめ
療育家具とは、発達に特性のある子どもたちが安心して過ごせるように工夫された家具のことです。姿勢が安定し、集中しやすくなることで、日常生活が少しずつ楽になります。療育家具は、子どもを助けるだけでなく、お母さんの負担や不安も軽くしてくれる“やさしい支援”のひとつです。「特別なこと」ではなく「身近にできる療育」として、家庭でも活用できることを知っていただけたら嬉しいです。