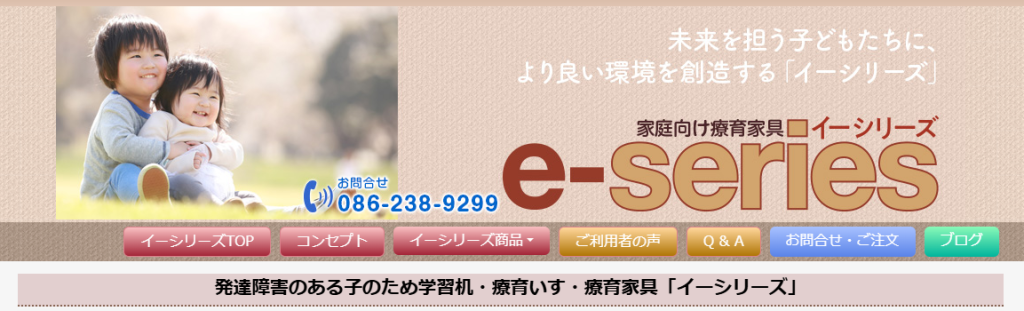「うちの子、じっと座っていられない…」そんな悩みを持つママは少なくありません。発達のグレーゾーンにある子どもは、座ること自体がとても大変なこともあります。私自身も専門家として、また母として、その難しさに向き合ってきました。ですが、小さな工夫で「座る力」は家庭でも育てることができます。今回は、自宅でできる簡単な工夫を具体的にご紹介します。
はじめに
「座りなさい」と声をかけても、子どもがすぐに立ち上がってしまう…。そんな日々に疲れてしまうママも多いでしょう。私も研究や関わりを通して、座ることが苦手な子がどれだけ多いかを知っています。「座る力」はただの姿勢の問題ではなく、学びや生活の基盤になるものです。だからこそ、焦らずに取り組むことが大切です。
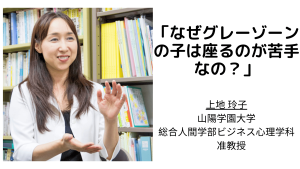
なぜ「座る力」がグレーゾーンの子に必要なのか
座ることが苦手な子にはいくつかの特徴があります。例えば、足をぶらぶらさせたり、体を左右に揺らしたり、すぐに立ち歩いてしまったりすることです。こうした行動は「わざと」ではなく、体の安定がうまくいかないから起こることも多いのです。
座る力が育つと、学習に集中できたり、食事を落ち着いてとれたり、集団の中で安心して過ごせたりします。小さな力ですが、将来につながる大切な基礎なのです。
自宅でできる!座る力を育てる3つの工夫
【工夫①】環境を整える ― 椅子や机を子どもサイズに合わせる
子どもの体に合わない椅子に座ると、足が床に届かず不安定になります。足がしっかり床につくことで、体が安定し、自然に座りやすくなります。私が関わったある子は、足台を置くだけで落ち着いて座れるようになりました。環境を整えることが第一歩です。
【工夫②】遊びながら練習 ― バランス遊びや短時間チャレンジ
「座る=長時間頑張ること」と思うと、子どもにとってハードルが高いです。まずは短い時間から始めましょう。例えば、バランスボールに座って遊ぶ、カードゲームを数分だけ座って楽しむなど。「遊びの中で座る」を積み重ねることで、座ることへの抵抗感が少なくなります。
【工夫③】集中を助けるアイテム ― クッションや療育家具の活用
座ることに苦手さがある子には、少し工夫された椅子やクッションも役立ちます。座面がやわらかいクッションや、体を支える形の椅子を使うと、自然に落ち着けることがあります。私が見てきた子の中には、専用の家具を使うことで「座れる時間が2倍になった」というケースもありました。
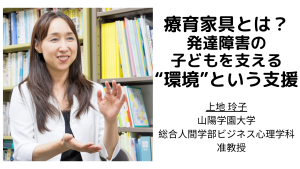
実際の事例から学ぶ「小さな工夫で変わった子どもたち」
私が関わった子の中に、いつも立ち歩いてしまい授業に集中できなかった子がいました。ところが、椅子の高さを調整し、足が床にしっかりつくようにしただけで、10分以上座れるようになったのです。小さな工夫でも、子どもの世界は大きく変わります。こうした経験を通して、「座る力」は一歩ずつ育てられるものだと実感しています。
おわりに
座ることは決して一瞬でできるようになるものではありません。けれども、家庭での工夫と専門家の知恵を少し取り入れることで、子どもは確実に成長していきます。大切なのは「無理やり座らせる」ことではなく、「座れる環境ときっかけ」をつくること。ママが一人で抱え込む必要はありません。子どもの可能性を信じて、一緒に小さな工夫から始めてみませんか。
まとめ
「座る力」を育てる工夫は、特別なことではなく、身近な環境や遊びの中にあります。足台を置く、短時間から挑戦する、クッションを使うなど、家庭でできることはたくさんあります。少しの工夫で子どもの自信や集中力が変わっていきます。みなさんのお子さんは、どんな工夫で座ることがラクになったでしょうか?よかったら、コメントで体験をシェアしてくださいね。