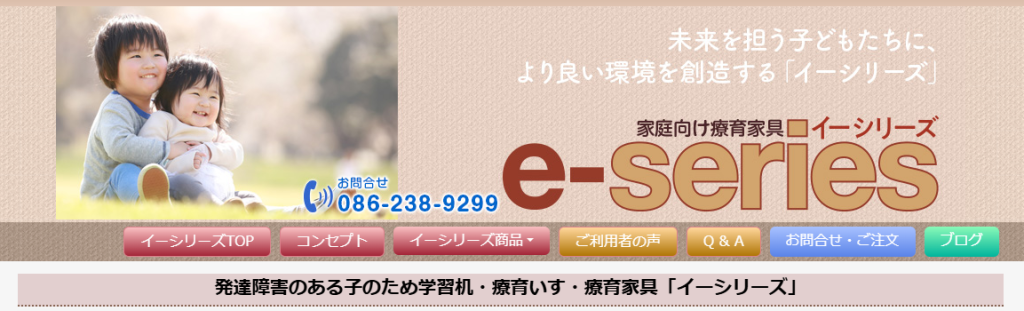「じっと座っていられない」「すぐ立ち上がってしまう」――そんな子どもの姿に、悩んでいるお母さんは少なくありません。特にグレーゾーンの子どもたちにとって、「座る」ということ自体が大きなチャレンジになることがあります。この記事では、なぜ座れないのか、その理由と家庭でできる工夫、さらに環境づくりのヒントをご紹介します。
「うちの子、どうして座れないの?」―ママたちの共通の悩み
私のもとにも「子どもが座っていられないんです」という相談がよく届きます。ご飯のときに立ち歩く、宿題を始めても数分で席を立つ…。そんな様子を見ると、「うちの子だけ?」と不安になる方も多いでしょう。でも実は、同じ悩みを抱えるお母さんはたくさんいます。座れないのは珍しいことではなく、理解と工夫で改善できることが多いのです。
グレーゾーンの子どもが「座れない」理由とは?
グレーゾーンの子どもが座れないのには、いくつかの理由があります。
- 注意が散りやすい
私が関わったある男の子は、宿題を始めてもすぐに周りの音や物が気になり、立ち上がってしまいました。これは、集中が続きにくい子どもによく見られる特徴です。 - 体の感覚が落ち着かない
別の女の子は、椅子に座るとすぐに足をバタバタさせたり、体をゆすったりしていました。体の感覚がうまく整わず、じっとしていること自体がつらかったのです。 - 椅子や机が合っていない
大人でもサイズの合わない椅子に長く座るのはつらいですよね。子どもも同じで、合わない家具が原因で「座れない」こともあります。
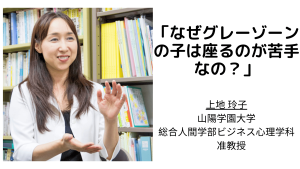
家庭でできる!「座れる時間」を少しずつ伸ばす工夫
座れない子どもに「ちゃんと座りなさい!」と言っても逆効果になることが多いです。そこで大切なのは「小さな成功を積み重ねること」です。
例えば、ある子どもとは「1分座れたらシールを貼る」という方法を試しました。最初は1分でも難しかったのですが、少しずつ「座れる時間」が伸びていきました。遊びの中に取り入れると子どもも楽しみながら続けられます。
また、「できたね!」と声をかけることで、子どもは自信を持ちます。その積み重ねが、座れる力を育てていきます。
家具や環境を工夫して「座れる」を応援する方法
座る力を助けるのは声かけだけではありません。環境の工夫も大切です。
例えば、背中をしっかり支えてくれる椅子や、足が床に届く高さの机を用意すること。こうしたちょっとした工夫が「座りやすさ」につながります。
私が見てきた子どもたちの中には、体に合った家具に変えただけで、驚くほど落ち着いて座れるようになった子もいました。療育家具や「イーチェスク」のような学習机は、そうした工夫が取り入れられています。子どもの成長を支えるために、環境を整えることも一つの方法です。
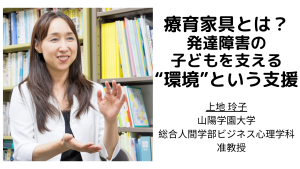
「座れない子」が「座れる子」に変わる第一歩は環境と理解から
「座れない」のは子どものわがままではなく、理由があります。その理由を理解し、少しずつ取り組むことで、子どもは必ず変わっていきます。大切なのは「叱ること」ではなく、「支えること」。環境を整え、家庭で小さな工夫を続けることで、子どもの力を引き出すことができます。
まとめ
座れない子どもを見ると、親として焦りや不安を感じることもあります。しかし「座れない」には理由があり、それを理解することが第一歩です。小さな工夫や環境の見直しで、子どもの「座れる時間」は必ず伸びていきます。もし「うちの子も…」と感じたら、今日からできる工夫を試してみませんか? 皆さんの体験や工夫も、ぜひコメントで教えてください。