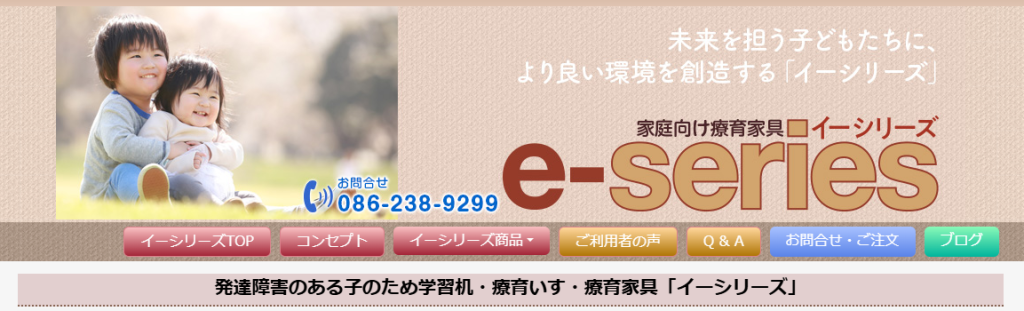「うちの子、どうしてじっと座っていられないんだろう…」そんなふうに悩んだことはありませんか?発達に気になる特性のあるお子さんにとって、「座ること」は実はとても大きなチャレンジです。特にグレーゾーンといわれる子どもたちは、見た目では分かりづらい困りごとを抱えていることも。この記事では、障がいのある子の母でもある私が、関わってきた子どもたちとの経験から「座る練習のコツ」や、「環境づくりの工夫」を分かりやすくお伝えします。
「うちの子、じっと座れない…」と感じたら読んでほしい
私が関わってきた中で、「座れないこと」を悩んでいるお母さんは本当に多くいます。「ふざけてるの?」「言うことを聞かないだけ?」とつい思ってしまうかもしれません。でも、多くの場合、子どもたち自身も「座っていたい」のに「じっとできない」ことで困っているのです。
発達障がいやADHDの特性を持つ子どもにとって、「座ること」は簡単ではありません。注意がそれやすかったり、体の感覚がうまくつかめなかったりすることがあるからです。私自身も、専門家として、そして母として、その姿をたくさん見てきました。
座れない理由は“わざと”じゃない!子どもの困りごとを理解しよう
ある日、私は療育の現場で、5歳の男の子と関わりました。彼は椅子に座るとすぐに立ち上がったり、体をゆらしたりして、集中が続かない様子でした。最初は「落ち着きがない」と言われていたのですが、実は座っているとお尻がムズムズして、不快に感じていたのです。
ADHDや発達障がいの特性には、「感覚の敏感さ」や「体のバランスを取るのが苦手」といった特徴があります。これは本人の努力やしつけの問題ではなく、生まれつきの脳の働きによるものです。ですから、「わざとじゃない」と理解することが、まず最初の一歩になります。
家庭でできる!楽しく取り入れる“座る練習法”3選
発達に特性のある子どもたちにとって、「座ること」を練習するには、楽しく・安心して・短い時間から始めることがポイントです。以下の3つの練習法は、実際に支援の現場で効果があった方法です。どれも家庭で気軽に取り組めます。
① “王さまゲーム”で「座る」を楽しく習慣に
ポイント:子どもの「想像力」と「役割遊び」を活かす
5歳の男の子Aくんは、いつも椅子に座るとすぐ立ち上がってしまう子でした。そこで私は、床にレジャーシートを敷いて「ここが〇〇くんのお城だよ」と伝え、「王さまになってお話を聞こう!」と声かけしました。
最初は1分座れたら「王冠シール」、3分で「ごほうびスタンプ」など、小さな達成を認めていきました。するとAくんは「もっと王さまになりたい!」と楽しみながら座ることに慣れていったのです。
👉 コツ:座る場所を「特別な場所」にすることで、自発的に座る気持ちが生まれやすくなります。
② 座る前に“ジャンプ遊び”でスイッチON!
ポイント:身体を動かしてから座ると落ち着きやすい
ある6歳の女の子Bちゃんは、座る前になるとソワソワして集中できない様子がありました。でも、座る前に「ジャンプ10回」「トンネルくぐり」「クルクルまわって止まる」などの動き遊びをしてから椅子に座ると、スッと落ち着くようになったのです。
これは「前庭感覚(バランス感覚)」を刺激することで、体の状態が整い、集中しやすくなる効果があるためです。難しく考えず、楽しく体を動かすだけでOKです。
👉 コツ:座る前にちょっと体を動かす“ウォーミングアップ”で、気持ちも身体も落ち着きやすくなります。
③ 「タイマー&ごほうび」で達成感を育てる
ポイント:見える時間と、がんばりを認める仕組み
タイマーを使って、「このタイマーが鳴るまで座ってみようね」と伝えると、多くの子どもたちは意外と楽しんで取り組んでくれます。特に“砂時計”や“キッチンタイマー”のように時間の見えるものはおすすめです。
ある7歳の男の子Cくんは、「3分座れたらシール1枚」というルールで挑戦を始めました。毎日少しずつ時間を延ばし、シールがたまったら好きなおやつを選べるようにしたところ、徐々に「座る」ことが習慣になっていきました。
👉 コツ:ごほうびは「がんばったね!」の声かけでも十分効果があります。
やってはいけないNG行動
- 無理に長時間座らせる
- 「ちゃんと座りなさい!」と怒る
- 他の子と比べてしまう
これらは子どもにプレッシャーを与え、かえって「座るのが苦手」という意識を強めてしまうことがあります。焦らず、お子さんのペースを大切にしてあげてください。
専門家おすすめ!“座る姿勢”を支える療育家具の力
子どもが安心して座れるようにするには、「どんな椅子に座るか」も大切です。ある6歳の女の子は、普通の椅子だと足がぶらぶらして落ち着かず、すぐに立ち上がってしまっていました。そこで、足がしっかり床につく高さの調節できる椅子に変えたところ、座る時間がぐんと伸びたのです。
私は、療育家具の開発にも関わっていますが、「子どもの体に合った環境」を整えることは、とても大切だと感じています。椅子の高さや、机との距離など、小さな工夫で子どもが「座っていられる」ようになることがあります。
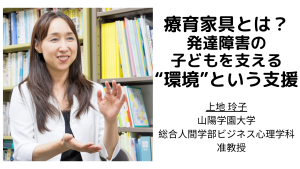
「座れるようになる」はゴールじゃない。大切なのは“その子らしさ”
「いつになったら座れるようになるの?」と焦る気持ち、よくわかります。でも、子どもにはそれぞれのペースがあります。座れるようになることだけがゴールではありません。
「少しだけ座って話が聞けた」「今日は立ち歩かなかった」――そんな小さな変化を見つけることが、親子にとっての希望になるはずです。
お母さん自身を責める必要はありません。私も、何度もそう思いながら子育てをしてきました。「座ること」がスムーズになるには、子どもだけでなく、環境や関わり方が大きく関係しているのです。
【まとめ】
「座る」という、あたりまえのように見える行動も、グレーゾーンの子どもたちにとっては、大きな努力が必要なことがあります。大切なのは、「なぜ座れないのか」を理解し、その子に合った関わり方を探していくことです。この記事では、家庭でできる工夫や、療育家具の効果も紹介しました。
あなたのお子さんの様子で、「あ、うちもそうかも」と思ったことがあれば、ぜひコメントで教えてください。どんな小さな一歩でも、みんなで共有していけたら嬉しいです。