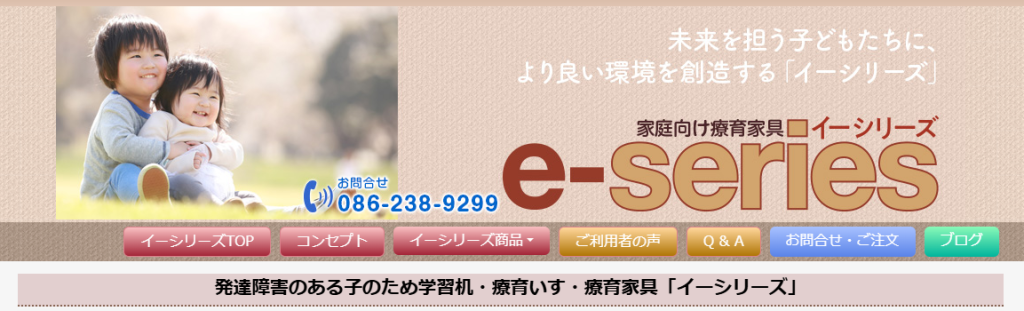「どうしてうちの子は、じっと座っていられないの?」——そんな悩みを抱えるお母さんは、決して少なくありません。静かに座って課題に取り組むことが求められる場面で、そわそわ動き出したり、何度も立ち歩いたりする姿に戸惑う方も多いでしょう。でも、その行動には“理由”があります。それは性格のせいでも、しつけの問題でもありません。私は、専門家として、そして当事者の母として、多くのグレーゾーンの子どもたちに関わってきました。この記事では、「座る」が苦手な子どもたちの背景と、家庭でできる工夫についてお伝えします。
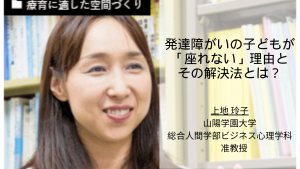
「うちの子、どうして座っていられないの?」と悩むママへ
私が出会った6歳の男の子、Kくんは、イスにじっと座っているのがとても苦手でした。保育園でも「また立ち上がっちゃった」と先生から報告があるたび、お母さんは落ち込んでいました。でも、Kくんに悪気はありません。絵本を読んでいても、5分ほどで足をバタバタさせ始め、気づくと机の下に潜っていたりします。
お母さんは「やる気がないのかな」「まわりの子はできているのに」と自分を責めていました。でも、よく観察すると、Kくんはじっと座っていること自体が大変そうでした。姿勢がすぐ崩れたり、おしりを何度も動かしたり。これは「座らない」のではなく、「座っていられない」状態なのです。
グレーゾーンの子が「座るのが苦手」な本当の理由
・身体の不安定さ(姿勢保持が難しい)
Sくん(小1)は、イスに座ってもすぐに体がぐらつき、背もたれにもたれたり、机にうつ伏せになったりします。本人に聞いてみると「なんか体が勝手に動く」と話してくれました。これは「体幹(たいかん)」といって、体の中心を支える力が弱いために、じっと同じ姿勢を保つのが難しいのです。
大人にとっては当たり前の「座る姿勢」も、この力が弱いと、それ自体が重労働になってしまうのです。
・感覚の過敏さや鈍さ
Tちゃん(年長)は、硬いイスに座るのをとても嫌がっていました。「おしりがイタイ」「足がチクチクする」と不快さを訴えます。これは「感覚過敏」といって、普通の人が気にならない刺激にも、強く反応してしまう状態です。逆に、鈍感な子は長く座っても違和感を感じづらく、姿勢が崩れても気づきにくいということもあります。
・注意のコントロールが苦手(ADHD傾向)
Mくん(小2)は、「今から国語の時間」と言われても、窓の外が気になったり、隣の子の動きにつられてしまったりします。目の前のことに集中し続ける力が弱く、すぐに気持ちが別の方向に向かってしまうのです。ADHDの傾向がある子に多く見られる特徴で、本人の意思とは関係なく注意があちこちに飛んでしまうのです。
・「座る」ことに意味を感じづらい背景
ある日、Yくん(小1)は私にこんなことを聞きました。「なんで座らないといけないの?」。私たち大人にとっては当たり前のルールも、子どもにとっては意味が見えなければ納得できません。「座る=学ぶ準備」という考えがまだ身についていない段階では、「動かないようにする」ことが目的になってしまい、ストレスになることもあります。
苦手さを「行動の問題」としないために
「じっとしなさい」「なんでまた立ったの?」と、つい声を荒げてしまう。これは多くのお母さんが経験していることです。でも、ある女の子が私に言った言葉を今も覚えています。「がんばってるけど、体が勝手に動いちゃうの」。この一言が、どれだけ私の考えを変えたか…。
子どもたちは、できないことで怒られる経験を繰り返すと、「私はダメなんだ」「どうせ怒られるし」と自信を失っていきます。大人が「なんでできないの?」ではなく、「どうしたらできるようになるかな?」という視点を持つことが大切です。
専門家ママが実践する「座れる環境」づくり
私は療育家具の開発に関わり、実際に多くの子どもたちに試してもらいました。その中で特に効果を感じたのは「イスの座面を小さくする」「足がしっかり床につく高さに調整する」といったシンプルな工夫です。
Kくんは、このイスに変えてから、座っている時間が10分から20分に伸びました。本人も「おしりがすべらない」「体がラク」と話していました。
また、30分ずっと座ることが難しい子には、「10分やったら、2分ストレッチタイム」と決めて、体を動かす時間を入れています。「動いていい時間」があることで、安心して座れるようになる子もいます。
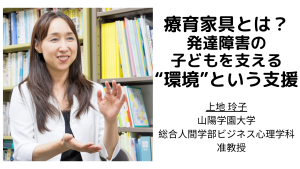
「座れない」は「できない」であって、「やらない」ではない
子どもが立ち歩くと、つい「ふざけている」と感じてしまいがちですが、実はそうではありません。多くの子が「がんばっても、じっとしていられない」ことに困っています。ある保護者の方が「何度も怒ってきたけど、あの子なりに努力してたんですね」と涙ぐまれたこともありました。
子どもの「困りごと」に目を向けることで、叱らずに支援する道が見えてきます。座れない子を責めるのではなく、その子が「座れる環境」を一緒につくっていくことが、親子にとっても大切な一歩になるのです。
まとめ
子どもが「座っていられない」とき、それはわがままや性格ではなく、「どうしても難しいこと」なのかもしれません。体の動かしにくさ、感覚の敏感さ、集中のしづらさ——それぞれに理由があります。私たち大人がその子の感じ方や困りごとに寄り添うことで、少しずつ「できる」ようになります。あなたのお子さんは、どんなときに安心して座れていますか? ぜひコメント欄で教えてください。みんなで情報をシェアしながら、子どもたちに合った環境づくりを一緒に考えていきましょう。