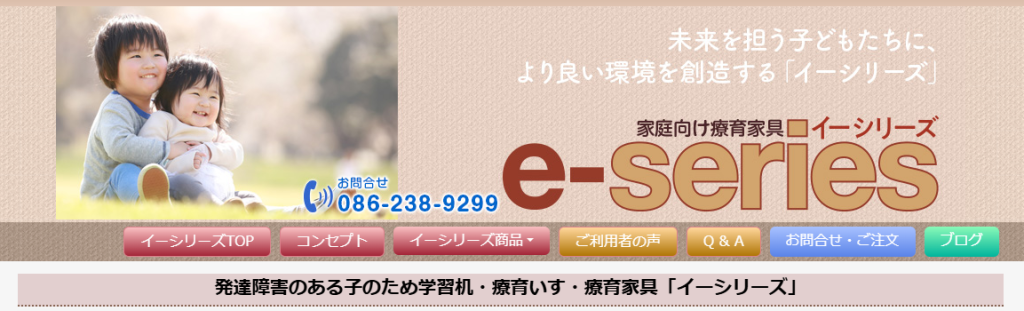「うちの子、すぐ立ち歩いてしまって…」そう悩むお母さんの声を、私は何度も聞いてきました。発達に特性のある子どもたちの中には、「じっと座ること」がとても苦手な子がいます。特にグレーゾーンといわれる、診断がつかないけれど困りごとがある子どもたちにとっては、大人の想像以上に「座ること」がつらい場合があります。今回は、そんな子どもたちの「なぜ?」に、療育と研究の現場からやさしくお答えします。
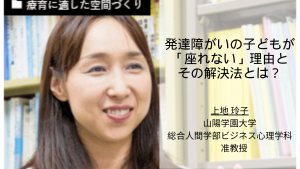
どうしてうちの子はじっと座っていられないの?
グレーゾーンの子の「座れない」悩みは意外と多い
お母さんたちから「ちゃんと座っててって言ってるのに!」という声をよく聞きます。でも実は、座れないことには理由があるのです。私が関わってきた子の中にも、授業中に何度も席を立ってしまう子がいました。先生に叱られるたび、しょんぼりしていました。でもその子は、「立とうと思ってるわけじゃない」のです。体が勝手に動いてしまう。そこに「努力不足」という言葉は、当てはまりません。
「グレーゾーン」とは?
診断名がつかないけれど、困りごとは確かにある
「グレーゾーン」という言葉は、診断がつかないけれど発達の特性がある子どもたちを表すときに使われます。たとえば、注意が散りやすい、集団行動が苦手、感覚に敏感など。でも、病院では「様子を見ましょう」と言われることが多く、支援も受けにくいのが現状です。私が関わってきたある男の子も、診断はなかったけれど、小学校の授業中に椅子に座っていられず困っていました。本人も「つらい」と言っていました。
座るのが苦手な理由①:感覚過敏や感覚鈍麻があるから
イスの硬さや衣類の締めつけが「気になりすぎる」子どもたち
ある女の子は、座るたびに「おしりが痛い」と言っていました。最初は「甘えてるのかな?」と思われていましたが、実は感覚過敏でした。感覚過敏とは、音や光、肌に触れるものが普通の人より強く感じられてしまう状態です。逆に、感覚に鈍い子もいて、長時間座っていることに気づかず、突然立ち上がってしまうこともあります。感覚は人それぞれで、見た目には分かりにくいのが特徴です。
座るのが苦手な理由②:じっとしていられないADHD特性
体が動いてしまうのは「わがまま」ではない
ADHD(注意欠如・多動症)の特性がある子どもは、じっとしているのがとても難しいことがあります。私が出会った男の子は、授業中に足をパタパタ、手はずっと何かをいじっていました。先生の話を聞きたくても、体の中に「動きたいエネルギー」がいっぱいなのです。「聞いてないの?」ではなく、「聞きたいけど体が先に動いちゃうんだね」と言ってあげるだけで、その子の表情がやわらかくなったのを覚えています。
座るのが苦手な理由③:姿勢を保つ筋力が弱い
実は体幹やバランス感覚の発達も関係している
一見元気な子でも、実は体を支える筋力が弱い場合があります。特に体幹(たいかん)といって、お腹や背中の筋肉がうまく使えないと、椅子に長く座っているのが苦しくなります。私が療育で見てきた子どもたちの中には、「机に寄りかかる」「すぐにズルズルずれていく」子も多くいました。これは、だらけているのではなく、姿勢を保つのが本当に難しいからなのです。
療育の現場で見えてきた!座れるようになるための工夫
家具・環境・声かけ…親にできることはたくさんある
座れない子に「ちゃんと座りなさい!」と言っても、うまくいかないことが多いです。でも工夫をすれば、座りやすくなることもあります。たとえば、足が床に届くように台を置いたり、姿勢を支えるクッションを使ったり。私たちが開発に関わった「療育家具」も、そうした子どもたちの困りごとから生まれました。また、「あと5分だけがんばろうね」と具体的な声かけをするのも効果的です。
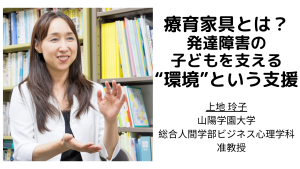
専門家ママの視点から:座れないことを「問題」と決めつけないで
わが子も苦手だったからこそ伝えたいこと
私自身も、発達に特性のある子どもを育ててきた母です。座れない子を見ると、つい「しつけができていない」と言われることもあります。でも、そうではありません。その子に合った環境や関わり方がまだ見つかっていないだけなのです。「できない」ではなく、「どうしたらできるか?」という視点で見ていくことが大切です。少しずつでも、子どもは必ず前に進んでいきます。
座れないのには理由がある。まずは「理解」から始めよう
今日からできる一歩を一緒に見つけましょう
子どもが座れないとき、大人はつい「なんでできないの?」と思ってしまいます。でも、その行動の裏には、目に見えにくい理由がたくさんあることを、私は現場で何度も見てきました。「できない」には、必ず意味があります。だからこそ、まずは「この子に何が起きているのか」を知ることから始めてみませんか?あなたの体験も、ぜひコメントで教えてください。一緒に子どもの未来を考えていきましょう。