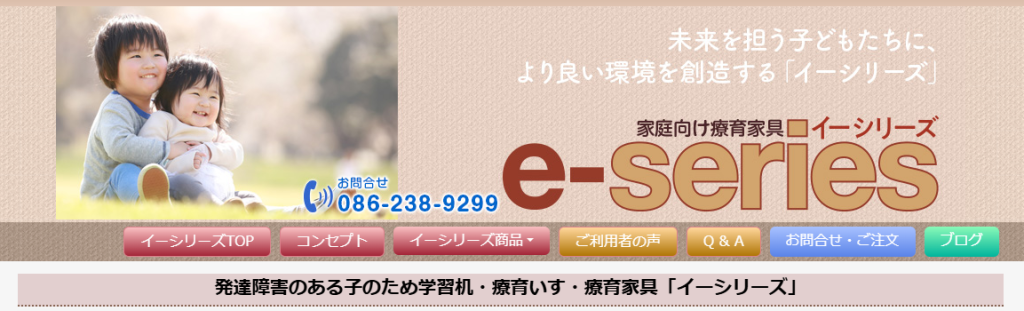「同じ年の子とちょっと違うかも…?」そんなふうに感じたことはありませんか? 発達障がいの“グレーゾーン”と呼ばれる子どもたちは、明らかな診断がつきにくいぶん、まわりに気づいてもらいにくいこともあります。でも、ちょっとしたサインを見逃さず、家庭でできる関わり方を知っておくだけで、子どもがぐっと楽に過ごせることもあります。この記事では、専門家であり母でもある私が、現場で出会った子どもたちとの経験をもとに、気づきのポイントと対応のヒントをお伝えします。
私も「もしかして…」と悩んだら
私はこれまで多くの発達に気がかりのあるお子さんと関わってきましたが、その中には「何か違うけど、説明できない」と感じる“グレーゾーン”の子どもたちがたくさんいます。あるお母さんは「保育園では大丈夫そうなんです。でも、家ではすぐ泣いたり、怒ったりで…」と話してくれました。子どもの発達は本当に一人ひとり違います。「育てにくさ」は、親のせいでも子どものせいでもありません。この記事では、「気づき」から「できること」まで、私の経験をもとにわかりやすくご紹介します。
こんなサイン、見逃していませんか? ― グレーゾーンの子に見られる初期の特徴
グレーゾーンとは、発達障がいの特徴があるけれど、診断がつかない、または診断がはっきりしない状態のことです。私が出会った男の子は、幼稚園では元気いっぱい。でも、集団での活動になると、すぐに立ち歩いたり、お友だちにちょっかいを出したり。集中が続かない様子がありました。また別の子は、服のタグや音にとても敏感で、泣いてしまうことがよくありました。「ちょっと育てにくいかも」と感じたとき、それは子どもからの「困っているよ」のサインかもしれません。
気になったときにまず試してほしい、家庭でできる3つの対応
1)関わり方を少し変えてみる
叱る前に、まず子どもがどう感じているかを想像してみましょう。「今は何をする時間なのか」を目で見てわかるようにしたり、声かけを短くしたりするだけでも、子どもが落ち着くことがあります。
2)家庭環境を整える
おもちゃがたくさん出しっぱなしになっていると、どこに集中していいかわからないことも。学習机のように「ここで○○をする」と場所を分けると、気持ちが切り替えやすくなります。音や光に敏感な子には、カーテンやマットなどで少し静かな環境を作るのもおすすめです。
3)ひとりで悩まない
市区町村の子育て支援センターや、保健師さん、療育の相談窓口は、お母さんの味方です。「気になるけど誰に相談していいかわからない」ときこそ、まず一歩だけ話してみてください。きっと、心が軽くなるはずです。
「うちの子はダメじゃない」母親としての私たちの役割とは
ある日、療育先で出会った女の子は、お友だちとのトラブルが多く、お母さんも悩んでいました。でも、彼女はお人形遊びが大好きで、細かいごっこ遊びがとても上手でした。その力を活かして、遊びの中でルールや会話の練習をしていくうちに、少しずつお友だちと関わる姿が増えてきたのです。「できないこと」ではなく、「できること」から支えていく。母親としての私たちの役割は、子どもの個性に気づき、それを育てていくことだと思います。
気づきは第一歩。今日からできる小さな一歩を
子どもが少し違って見えると、不安になるのは当然のこと。でも、その「気づき」が、子どもを理解する第一歩になります。私たち母親は、完璧である必要はありません。ただ、わが子のためにできることを一つずつ試していけば、きっと子どもにも伝わります。読者の皆さんはどう感じましたか? ぜひコメントで、お子さんとの日常や気づいたことをシェアしていただけたら嬉しいです。あなたの経験が、きっと誰かの力になります。