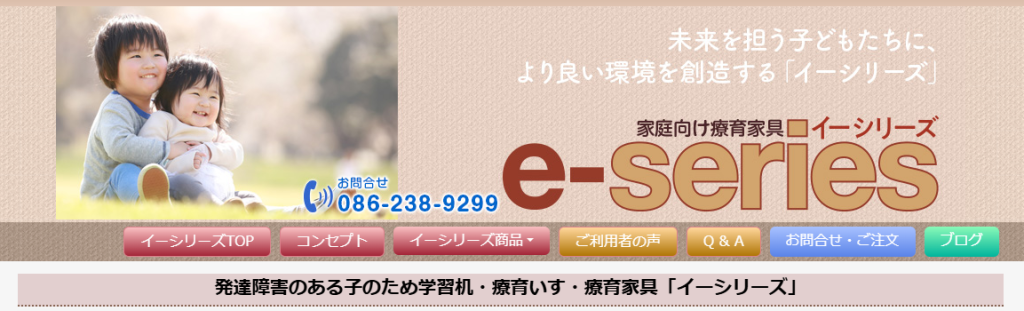― 専門家ママが語る、見えにくい悩みと家庭でできる一歩 ―
「なんとなく育てにくい」「でも診断はつかない」——そんな悩みを抱えるお母さん、多くいらっしゃいます。今回は、発達障害の“グレーゾーン”にいる子どもたちがどんな困りごとを抱えているのか、そして家庭でできる支援について、専門家であり母親でもある筆者がやさしく解説します。家庭での工夫が、子どもの力を引き出す第一歩になるかもしれません。
【はじめに】「グレーゾーンってどういうこと?」──見逃されやすい子どものサイン
「グレーゾーン」とは、発達障害の診断がはっきりとは出ていないけれど、生活や学びに困りごとを抱えている子どもたちのことです。
たとえば、学校でお友だちとトラブルが多かったり、注意されたことをすぐに忘れてしまったり…。でも病院では「診断まではいかないですね」と言われてしまう。そんな子たちがたくさんいます。
私自身、障害のある子を育ててきた母として、そして研究者として、たくさんのグレーゾーンの子と関わってきました。今回は、そうした子どもたちの「見えにくい困りごと」と、家庭でできる支え方についてお話しします。
【子ども編】グレーゾーンの子が抱えがちな「困りごと」トップ3
◆ 集団行動が苦手なのはわがままじゃない
ある小学校1年生の男の子は、運動会の練習になると急に教室から出て行ってしまいました。先生は「わがままを言っている」と思っていたそうですが、実は大きな音や声が苦手で、怖くてその場にいられなかったのです。
見た目には「変わった行動」に見えるかもしれませんが、その子なりの理由があるのです。
◆ 感覚の過敏さ・鈍さが「できない理由」になっている
別の子は、手を洗うのが苦手でした。理由を聞いてみると「水が冷たくて痛い」とのこと。実際に私も試してみると、少し冷たい程度。でもその子にとっては、まるで氷のように感じていたようです。
感覚の感じ方は人それぞれです。それが原因で「できない」こともあるのです。
◆ 集中できない・落ち着かない=ADHD傾向?
いつも席を立ってしまう、話の途中で割り込んでしまう…。そんな行動が多い子がいました。まわりの大人から「落ち着きがない」と注意されてばかり。でも、実は頭の中がいつもフル回転していて、止められない状態でした。
これは、ADHD(注意欠如・多動)傾向のある子に多く見られる特徴です。でも本人にとっては「頑張ってるのに止められない」ことが多いのです。
【親編】ママたちが感じている「孤独」と「不安」のリアル
◆ 育児書どおりにいかない、でも誰にも相談できない
あるお母さんは、「子どもが言うことを聞かないのは私の育て方が悪いのかも」と悩んでいました。でも、誰に相談しても「そのうちよくなるよ」と軽く言われてしまいます。
そんな言葉では、気持ちは楽になりませんよね。
◆ 「わがままに見える」「しつけが足りない」と言われるつらさ
スーパーで子どもが大声を出すと、知らない人から冷たい目で見られる。そんな経験をしたママも少なくありません。でも、それは「しつけ不足」ではなく、「今、その子にとってつらいことが起きている」だけなのです。
◆ 専門家ママも悩んできた道だからこそ、伝えたいこと
私もたくさん悩んできました。「母親なのに、なんでわかってあげられないんだろう」と自分を責めたこともあります。でも、子どもと向き合いながら、少しずつ見えてきたことがあります。それは、「親だけでがんばらなくてもいい」ということです。
【家庭支援】専門家がすすめる!家庭でできる3つのサポート術
◆ ①環境を整える:「叱らなくて済む」家具の力
たとえば、ある男の子は宿題を始めるまでに30分以上かかっていました。でも、周囲のものが目に入らないように学習机を工夫したところ、すぐに座って集中できるようになったのです。
私たちが開発した「療育家具」も、こうした子の集中を助ける家具の一つです。環境を変えるだけで、子どもの力が自然と引き出されることもあるのです。
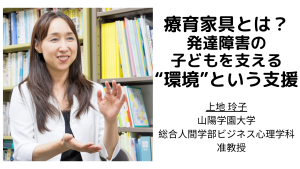
◆ ②気持ちを言葉に:親子でできる簡単なコーピング練習
「イヤだ!」「もうムリ!」と言って泣いてしまう子に、「どうしてそう思ったの?」と聞くのは難しいことです。代わりに、気持ちのカードや絵を使って「今、悲しい?」「イライラしてる?」と選ばせる方法があります。
言葉にすることで、気持ちを整理しやすくなります。
◆ ③「がんばらなくていい」声かけ習慣のすすめ
子どもが失敗したとき、「なんでできないの?」と言いたくなることもあると思います。でも、そんなときは「がんばったね」「最後までやってえらかったよ」と伝えてみてください。
できたことに目を向ける声かけが、子どもを前向きにします。
【おわりに】「普通じゃなくていい」──子どもと一緒に育つ毎日へ
グレーゾーンの子どもたちは、「普通」や「当たり前」と言われることにうまくなじめないことがあります。でも、それはダメなことではありません。
子どもの得意なこと、好きなことを見つけて伸ばしていくこと。それが本当の「育ち」だと私は思います。
家庭は、子どもが安心して戻れる場所。お母さんも、子どもと一緒に少しずつ成長していけばいいのです。
あなたのがんばりは、きっと子どもに伝わっています。焦らずに、今日できることから始めていきましょう。
グレーゾーンの子どもたちの困りごとは、見えにくく、誤解されやすいもの。でも、ちょっとした理解と工夫で、日々の暮らしがずっと楽になることがあります。今回ご紹介した内容が、子育てに悩むお母さんたちの小さなヒントになればうれしいです。あなたのお子さんには、どんな「困りごと」がありますか?ぜひコメントで教えてください。