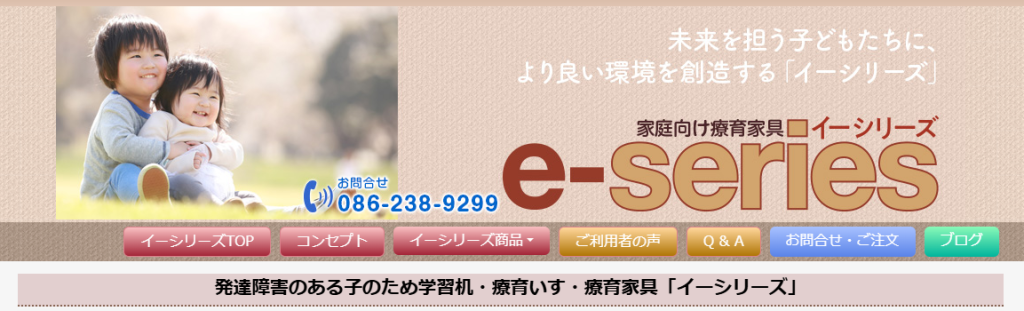「うちの子、じっと座っていられない…」そんな悩みを抱えていませんか?発達障がいのある子どもは、椅子に長く座るのが苦手なことが多く、勉強や食事の時間に困ることもあります。しかし、「座る力」は工夫次第で伸ばすことができます!本記事では、発達障がい児が座りやすくなる環境の整え方や、楽しく体幹を鍛える方法を紹介します。また、母親としての視点を活かし開発した「療育家具」の活用法もお伝えします。座ることが楽しくなれば、学習や生活の質もアップ!お母さんが一人で悩まず、子どもの成長をサポートできるよう、具体的なアイデアをたっぷりお届けします。
1. 発達障がい児の「座る力」とは?
「じっと座っていられない…」発達障がい児を育てる母の悩み
「うちの子、椅子に座っていられない…」そんな悩みを抱えているお母さんは多いのではないでしょうか?食事中に立ち歩いてしまう、宿題を始めてもすぐに別のことに気を取られてしまう…。発達障がいのある子どもたちは、集中して座ることが苦手な場合が多く、親としてはどう対応すればいいのか悩んでしまいます。
座る力が身につくと、学習や生活がどう変わるのか?
「座る力」がつくと、子どもは落ち着いて学習や遊びに取り組めるようになります。例えば、学校で授業に集中できる時間が増えたり、家での宿題や食事の時間がスムーズになったりします。また、正しく座ることで姿勢がよくなり、疲れにくくなるというメリットもあります。座ることが苦手な子どもにとって、「座る力」を育てることは、学習だけでなく生活全般をより良くする大切なステップなのです。
2. 「座る力」が育たない原因とその影響
ADHD・ASDの子どもが「座るのが苦手」な理由とは?
発達障がいのある子どもが座るのを苦手とする理由はいくつかあります。
- 体の感覚が不安定:体幹の筋肉が弱かったり、バランスを取るのが苦手だったりする子は、椅子に座っているのがつらく感じることがあります。
- じっとしているのが苦手:特にADHDの子どもは、動いている方が落ち着く場合があります。動かずにじっとしていることが、かえってストレスになることも。
- 環境が合っていない:机や椅子の高さが合っていないと、座ること自体が苦痛になります。また、周りに気が散るものが多いと、注意がそれてしまいがちです。
長時間座れないことが学習や日常生活に与える影響
座るのが苦手だと、学校の授業中に落ち着いていられなかったり、家で宿題が進まなかったりすることがあります。さらに、食事中に席を立ってしまうことが多いと、栄養バランスの良い食事をとることが難しくなることも。親子ともにストレスが増えてしまう原因になります。
3. 母としてできる!発達障がい児の「座る力」を伸ばす方法
環境を整える!子どもに合った椅子・机選びのポイント
「座る力」を伸ばすためには、まず子どもに合った環境を整えることが大切です。
- 椅子と机の高さを調整する:足がしっかり床につく高さの椅子を選びましょう。足がぶらぶらすると体が不安定になり、落ち着きにくくなります。
- 背もたれやクッションを活用する:姿勢を保ちやすくするために、背もたれのある椅子や、クッションを使うのもおすすめです。
- 気が散るものを減らす:学習スペースをシンプルにして、余計な刺激を減らしましょう。
遊びながら身につける!体幹を鍛える簡単エクササイズ
座る力を育てるためには、体幹を鍛えることが効果的です。遊びの中で楽しく取り入れられるエクササイズを紹介します。
- バランスボールに座る:楽しみながら自然と体幹を鍛えることができます。
- 動物のまねっこ遊び:クマ歩きやカエル跳びなど、全身を使う遊びは体幹の強化につながります。
- 一本橋を渡るゲーム:家の中でタオルやマットを使って「一本橋」を作り、その上を歩く遊びもバランス感覚を養うのに役立ちます。
無理なく取り組むコツ!親子で楽しく座る習慣を作る
「座ること」を無理に強制すると、子どもにとって苦痛になってしまいます。まずは短い時間から始めて、「◯分座れたらシールを貼る」といったゲーム感覚の工夫を取り入れるのもよいでしょう。また、お母さんが「一緒に座る」ことで、子どもも安心しやすくなります。
4. 実際に効果があった!療育家具と工夫の実例
専門家×母親の視点から開発!発達障がい児向けの学習机【イーチェスク】とは?
私自身、障がいのある子どもの母として、「うちの子に合った椅子と机がない…」と悩んでいました。そこで、専門家としての知識と母親としての経験を活かし、療育家具【イーチェスク】を共同開発しました。
この学習机は、子どもの成長に合わせて高さを調整できるほか、集中しやすい工夫が施されています。実際に使用した家庭では、「以前よりも落ち着いて宿題ができるようになった」との声が多く寄せられています。
実際の使用例&「座る力」が伸びた成功事例
イーチェスクを使い始めたお子さんの中には、「30分以上座れるようになった」「学習に取り組む姿勢が変わった」という変化を感じたご家庭もあります。環境を整えることで、子どもが無理なく「座る力」を育てることができるのです。
5. まとめ:母親の悩みを減らし、子どもの可能性を広げよう
「座る力」が育つことで変わる未来
座る力が育つと、学習への集中力が高まり、日常生活もスムーズになります。無理なく「座る習慣」を身につけることで、子どもの成長をより良いものにできるのです。
お母さんが一人で抱え込まないために
子どもの「座る力」を伸ばすには、お母さんの負担を減らすことも大切です。家具の工夫や、楽しい習慣作りを取り入れることで、無理なく続けられる方法を見つけましょう。そして、決して一人で悩まないでください。同じ悩みを持つ仲間や、専門家の力を借りながら、一歩ずつ進んでいきましょう。
発達障がい児の「座る力」を伸ばすことは、学習や日常生活の向上につながります。そのためには、子どもに合った椅子や机を選び、楽しく体幹を鍛える工夫が大切です。無理に座らせるのではなく、親子で楽しみながら習慣化することで、子どもも前向きに取り組めるようになります。また、療育家具を活用することで、より快適に座る力を伸ばすサポートが可能です。お母さんが一人で悩まず、環境を工夫したり、専門家の知識を取り入れたりしながら、子どもと一緒に成長していけることを願っています。