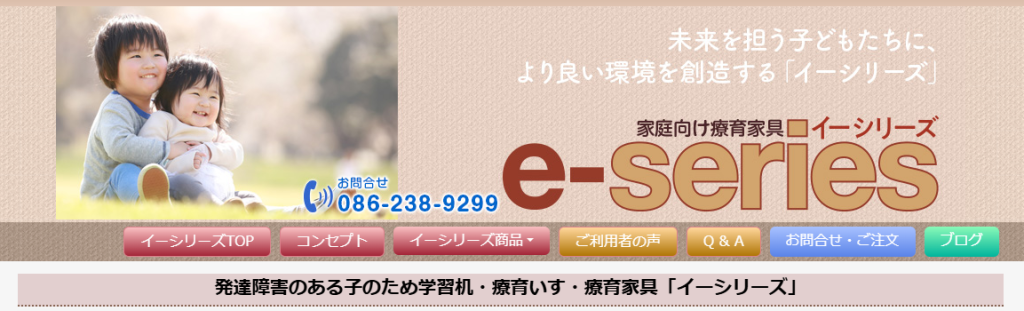「うちの子、どうして座れないんだろう?」と悩んだことはありませんか?発達障がいのある子どもにとって、「椅子に座る」ことは大人が思う以上に難しい挑戦です。その原因には、感覚過敏や筋力の弱さ、外部刺激への敏感さなど、さまざまな理由が隠れています。本記事では、子どもの「座れない」理由を解明し、実際に役立つサポート方法を具体的に解説します。また、子どもの特性に寄り添った療育家具の活用法についても触れ、家庭でできる実践的な工夫をご紹介します。お子さんの可能性を広げるヒントを一緒に探しましょう!
「座れない」には理由がある:まずはその背景を知ることから始めよう
「どうしてうちの子は座っていられないんだろう?」と悩むお父さんやお母さんは多いです。発達障がいを持つ子どもたちは、ただ「落ち着きがない」わけではなく、「座れない」ことには理由があります。
たとえば、椅子の座り心地が気持ち悪かったり、周りの音や動きに気を取られてしまったり、じっとしているのが苦手だったりします。また、体を支える筋肉が弱くて、座るのが疲れてしまう子どももいます。
さらに、感覚の敏感さや鈍感さが原因となる場合もあります。たとえば、座ったときの体の圧力や触感が気になりすぎる、逆に体がどこにあるのか分かりにくいと感じる子どももいます。
「座れない」には一人ひとり違う原因があります。まずはその理由を知ることが大事です。子どもの行動をよく観察して、「どんなときに座れないのか」を探ってみましょう。
なぜ座れないのか?発達障がい児特有の感覚や行動を知ろう
発達障がいのある子どもが「座れない」理由は、大きく分けて以下のようなものがあります。
- 椅子の座り心地が嫌い:椅子が硬すぎたり、冷たかったりして気持ち悪いと感じることがあります。特に感覚過敏のある子どもにとっては大きなストレスです。
- じっとしているのが苦手:体を動かさずにいるのがつらい子どももいます。これはADHDの特徴の一つで、「動くことで集中力を保とうとしている」場合があります。
- 集中しづらい環境:周りの音や光、他の人の動きなど、外部からの刺激に気を取られてしまうことがあります。こうした刺激が多い環境では、椅子に座ることが苦痛に感じることがあります。
- 体を支えるのが大変:筋力が弱かったり、体のバランスを取るのが難しかったりする子どもは、座る姿勢を保つだけで疲れてしまいます。
- 視覚や聴覚の刺激に敏感:例えば、机の上の模様や部屋の中の時計の音など、大人には気にならないような小さな刺激が集中を妨げることがあります。
これらの理由を理解することで、「どうして座れないのか」の答えが見えてきます。そして、「どうすれば座れるのか」を考えるための土台となります。
子どもの「座る」をサポートするための実践的なアプローチ
子どもが「座れる」ようになるには、環境を整えたり、少しずつ練習を重ねたりすることが大切です。以下の方法を試してみてください。
- 短い時間から練習する:最初は5分だけ座る練習をして、少しずつ時間を延ばします。成功したらたくさんほめてあげましょう。「できた!」という達成感が子どもの自信につながります。
- 遊びで体を鍛える:バランスボールやトランポリンで遊ぶと、体のバランスを取る力がつきます。これにより、座るときの姿勢が安定します。
- 環境を整える:
- 静かな場所で作業をする。
- 椅子にクッションを置いて座り心地をよくする。
- 足が床につかない場合は足置きを使う。
- 感覚に合った道具を使う:感覚過敏がある子どもには柔らかい座布団や体にフィットする椅子を用意するのがおすすめです。
- 無理をしない:長時間座らせようとせず、こまめに休憩を入れることで、子どものストレスを軽減できます。
さらに、子どもの得意なことや好きなことを取り入れることで、楽しみながら練習できます。たとえば、好きなキャラクターの椅子を使ったり、お気に入りの音楽を流したりすると効果的です。
療育家具の役割:子どもの特性に合わせた環境づくり
子どもが「座れる」環境を作るために、療育家具を使うのもおすすめです。療育家具は、子どもの体や特性に合わせて設計されています。
- 机の角度を変えられる:
- 平らな机では集中しづらい子どもも、机を少し傾けると姿勢が楽になり、勉強に取り組みやすくなります。
- 例えば、イーチェスクの学習机は、子どもに合わせた角度調節が可能です。
- 姿勢を支える椅子:
- 子どもの体に合った椅子を使うことで、体が安定し、長時間座るのが楽になります。
- 足が床につかない場合も、フットレストを使えば正しい姿勢を保てます。
実際に療育家具を使った親御さんからは、「子どもが前よりも落ち着いて勉強に向かえるようになった」「座る時間が少しずつ長くなった」という声が多く寄せられています。家具はただの道具ではなく、親子の生活を支える大切なパートナーです。
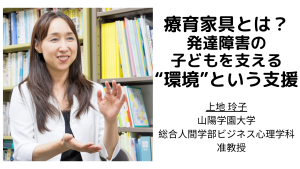
子どもと一緒に成長する:「座れない」を受け入れ、未来を支えるサポートへ
「座れない」という悩みは、子どもと親が一緒に向き合うことで少しずつ解決できます。子どもの特性を理解し、無理せず楽しく取り組むことが大切です。
環境を整えたり、少しずつ成功体験を積み重ねたりすることで、「座れる」時間が増えていきます。そして、子ども自身が「できた!」と感じることが、自信や成長につながります。
また、親が子どもの行動を「受け入れる」ことで、子どもは安心感を得ることができます。「座る」という行為を無理強いせず、「その子に合ったやり方」を見つけることが鍵です。
私たち大人がサポートすることで、子どもたちは自分らしく成長することができます。一歩ずつ前進しながら、親子の絆を深めていきましょう!親子の笑顔が増えるよう、応援しています。
まとめ
「座れない」理由を理解することで、親子の新しい一歩が始まります。子どもの特性に合った環境を整えたり、少しずつ練習を積み重ねたりすることで、子どもが座ることに自信を持てるようになります。また、療育家具の活用は、親子の生活をより快適にし、子どもの成長を支える大きな力になります。「座れない」は決してゴールではなく、「どうすれば座れるか」を親子で一緒に見つけていく過程そのものが大切です。子どもの成長と笑顔を支えるために、できることから始めてみましょう。