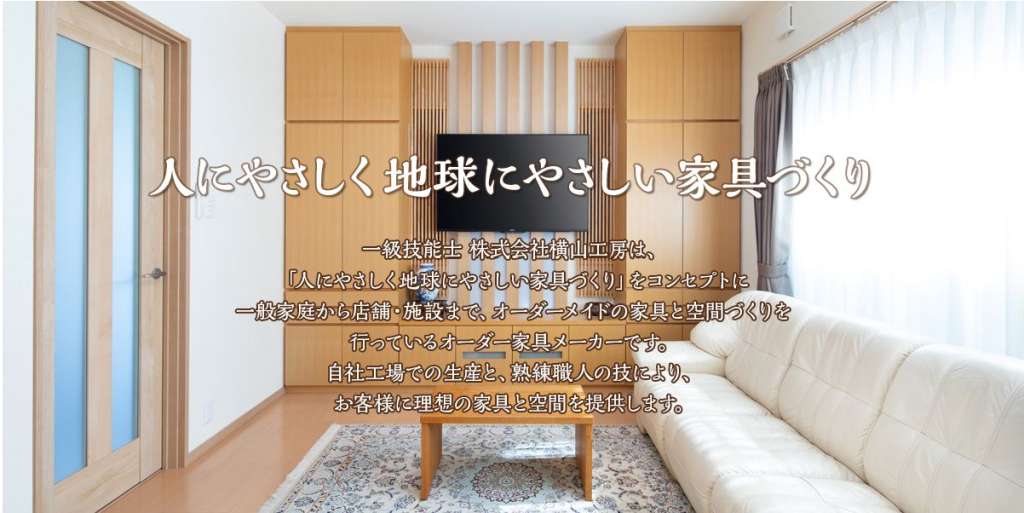木工を楽しむ上で欠かせない道具、のこぎり。正しい使い方を知ることで、作業の精度や効率が格段に向上します。今回は、木工歴30年以上の一級家具製作技能士である私が、のこぎりの基本中の基本である「持ち方」について詳しく解説します。意外と知られていないポイントも多いので、初心者から経験者までぜひ参考にしてください。
掌が下になる持ち方が基本
まず最初に、のこぎりを持つ際の手の向きについて説明します。正しい持ち方は、掌が下を向く形です。 これを聞いて「そんなの当たり前だろう」と思う方もいるかもしれませんが、実際には掌を横に向けて持っている方を多く見かけます。この持ち方をすると、引いたときに刃がぶれてしまい、正確な切断が難しくなります。特に繊細な加工が求められる家具製作において、このぶれは致命的です。
間違った持ち方が生む問題
掌を横にして持つと、のこぎりを引く際に手首が余計な動きをしてしまい、切断面が荒れる原因となります。また、刃が木材に食い込みすぎたり、逆に浅すぎたりして、一定のリズムで切ることが難しくなります。これでは美しい仕上がりは期待できません。
日本ののこの特徴を理解する
日本ののこぎりは「引いて切る」ことが特徴です。これは、欧米の押して切るタイプののこぎりとは根本的に異なります。この違いを理解していないと、正しい持ち方や使い方が身につきません。
実は、私自身も子どもの頃、この「引いて切る」という意味がよく分からず、疑問に思っていました。のこぎりは前後に動かす道具だから、刃がどちらを向いていても同じだろう、と考えていたのです。しかし、実際に経験を積むうちに、この考えがいかに浅はかだったか気づかされました。
刃の向きと切断の精度
日本ののこぎりの刃は、引くときに力が集中するように設計されています。この設計のおかげで、少ない力で効率的に木材を切ることができるのです。一方、刃の向きを意識せずに使うと、刃が木材に引っかかったり、切断面がガタガタになったりします。この違いを体感するには、正しい持ち方でのこぎりを使い、木材を切る練習を重ねることが大切です。
持ち方の実践ポイント
正しい持ち方を実践するためのポイントをいくつかご紹介します:
- 重心を意識して握る
握りすぎず、適度な力加減でのこぎりを持ちます。力を入れすぎると刃の動きがスムーズにならず、逆効果です。重要なことはバランスです。のこの重心を感じながら、のこが軽く感じれるところをもってください。 - 手首の角度に注意する
手首は固定し、肘から先を使ってのこぎりを動かします。手首を動かしてしまうと、刃がぶれやすくなります。 - 姿勢を整える
切断する木材に対して体を正面に向け、安定した姿勢を保ちます。足を肩幅に開き、重心を低くすると安定感が増します。
練習で精度を高める
正しい持ち方を身につけたら、繰り返し練習して切断の精度を高めましょう。最初は真っ直ぐ切ることが難しいかもしれませんが、焦らず少しずつ慣れていくことが大切です。初心者の方は、柔らかい木材で練習するのがおすすめです。
職人でも知らない人が多い理由
驚くべきことに、この「掌を下に向けて持つ」基本ができていない職人も少なくありません。なぜなら、のこぎりの持ち方や使い方について、深く考える機会が少ないからです。道具の使い方を自己流で覚えてしまうと、間違った方法が癖になってしまいます。
まとめ
のこぎりの持ち方は木工の基礎中の基礎ですが、正しく身につけている人は意外と少ないものです。掌を下に向けて持ち、日本ののこぎりの特徴である「引いて切る」動きを最大限に活かすことが、美しい仕上がりへの第一歩です。
あなたもぜひ、正しい持ち方を意識してのこぎりを使ってみてください。長年培われた日本の道具の知恵を実感しながら、木工の楽しさを味わいましょう。