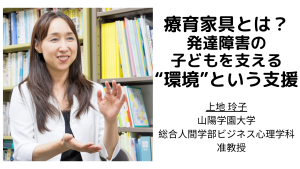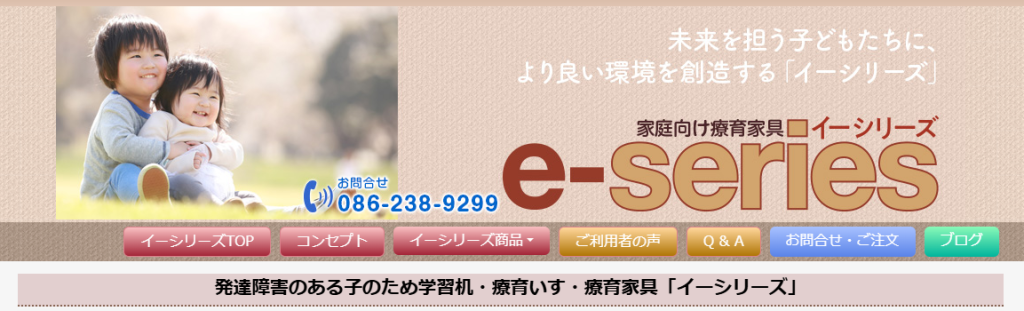発達障害の中でも特に多動性や衝動性が高いお子さんは、じっと座って課題に取り組むことが苦手な場合が多いですね。好きなゲームなどには集中できても、学校の宿題や試験勉強のような好きではない課題になると、集中力が続かないことがあります。椅子に座っていても立ち上がりたくなったり、気が散ったりしてしまうのは、よくある現象です。
では、どうすれば安定して座れるようになるのでしょうか?今回は、私が母親であり専門家として研究してきた知見を基に、具体的な解決策をご紹介します。
家庭での椅子と机の見直し
まず、お子さんが普段使用している椅子と机を確認してみましょう。特に以下のポイントをチェックしてください。
- 足が床にしっかりついているか?
- 足裏を床にべったりつけることで、体が安定し、集中力を高める効果があります。ただし、足で床を蹴って椅子ごと動かしてしまうこともあるため、椅子が動きにくい構造であることが理想です。
- 肘を90°に曲げて机に置けるか?
- 肘を机に安定して置くことで、腕の疲れを軽減できます。これは大人も同じですが、発達障害のお子さんの場合、感覚過敏があるため疲れを強く感じやすい傾向があります。
- 囲まれた空間を作る工夫
- 椅子の座面が小さめで、腰や肘を囲むような板があると、体が安定しやすくなります。また、囲まれた空間が集中力を高める助けにもなります。
さらに、椅子の高さが適切でないと、体のバランスを崩してしまうこともあります。足置き台を活用することで、より安定した座り方が可能になりますので、状況に応じて調整してみてください。
視界のコントロール
多動性の高いお子さんは、視界に入るものに気を取られやすいです。そのため、以下の工夫が効果的です。
- パーテーションを活用する 課題以外のものが視界に入らないようにすることで、集中力を維持しやすくなります。テレビ、カレンダー、時計など気が散りやすいものを隠してみてください。
- シンプルな作業スペースを用意する 机の上は必要最低限の物だけにし、カラフルな装飾や刺激の多いアイテムは置かないようにしましょう。お子さんが取り組む課題にフォーカスできる環境作りが鍵です。
私の研究—特別な机と椅子の効果
2017年、私は発達障害のある子どもたちを対象に、特別な学習机と椅子の効果を研究しました。この特別な机と椅子は、以下の特徴を持っています:
- 座面を小さくし、横に大きな板をつけた椅子
- 足置き板を広くした設計
- 机にくぼみをつけて体がすっぽりはまるデザイン
対照として一般的な学習机と椅子を使用し、学習中の集中度や正確性、姿勢の安定性を比較しました。その結果、特別な机と椅子を使用した場合、集中力が高まり、正確に課題をこなす率が大幅に向上しました。また、姿勢の安定度も顕著に改善されました。
この研究結果は、環境の改善が子どもの集中力にどれだけ影響を与えるかを示しています。お子さん一人ひとりの特性に合わせて、家具を選ぶことが重要です。

叱らない環境を作る
発達障害のお子さんにとって、叱られながら学習することは大きなストレスとなります。それが続くと二次障害(自信の喪失や自己否定感など)を引き起こしかねません。叱られる心配がない環境で、楽しく学ぶことができる工夫が重要です。
例えば、
- ポジティブな声かけ “よくできたね!”などの励ましで、子どもの自己肯定感を育てる。
- 達成感を得られる小さな目標設定 無理なくクリアできる課題を設定し、成功体験を積み重ねる。
また、課題を進める中で子どもがストレスを感じている様子があれば、無理に続けさせるのではなく、一度休憩を取らせることも大切です。リラックスできる時間を挟むことで、次の取り組みに意欲が湧きやすくなります。
支援者としての親の役割
発達障害のお子さんを持つ親は、時に専門家以上の観察力と適応力が求められることがあります。お子さんの特性を理解し、その特性に合ったサポートを提供することが重要です。
例えば、
- 日々の変化を記録する お子さんがどのような環境で集中しやすいか、逆にどのような場面で困難を感じているかを記録しておくと、支援の質を向上させる助けになります。
- 専門家との連携 支援学校や療育施設、医療機関などの専門家と情報を共有し、家庭と外部支援の連携を強化することで、お子さんに最適な環境を提供できます。
親が無理なく続けられるサポートを意識することが、お子さんとの信頼関係を築く基盤となります。
おわりに
子どもが安定して座り、集中して課題に取り組める環境作りは、親にとっても大きな安心感をもたらします。私自身も母親として試行錯誤を繰り返しながら、研究者としての視点を取り入れてきました。最も大切なのは、お子さんが楽しく、自分らしく学べる環境を整えることです。
「私にとっての療育とは子供が幸せに生きていくための力を身につけるもの」です。この考えを基に、お子さんが伸び伸びと成長できる支援を続けていきたいと考えています。
子どもの可能性を最大限に引き出すためには、親としての努力と専門家の知見の両方が必要です。このような取り組みが、発達障害のお子さんの未来をより豊かにする一助となれば幸いです。